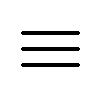学生に対する講義を通して「教育」について考えたこと“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.25))
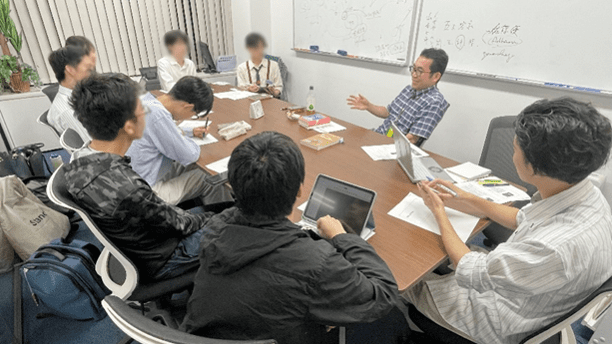
今週月曜日に第8回IISIA読書会を実施した。これは、ブログ(IISIA教育の歴史を振り返る(その1) (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.17)))で取り上げた2019年までのプレップスクールをはじめとする活動や、2020年以降、弊研究所ファウンダー/代表取締役CEO・原田武夫を講師とした都内大学での自主ゼミ、国立大学、及び私立大学での講義実施が形を変え、2025年IISIA読書会として戻ってきたものである。IISIA読書会は、書籍から“過去を正しく知り、未来を見据えるアントレプレナーシップ教育”をテーマとしている。具体的には、テーマに沿った課題図書が2~3冊提示され、各学生がこれを精読した上で、IISIA読書会内でグループ毎10分間のプレゼンテーションを行う。これをもって、弊研究所代表・原田武夫による解説とそれに対するレクチャーが行われるというものである。今週17 日(月)が2025年IISIA読書会の初回(2024年度第8回)であった。
しかし、今回は上記の講義形式とは異なり、筆者が講義の大半を担うこととなった。テーマは「仮想通貨の台頭とその行方を予測する」 とし、通貨の歴史から株式投資、そして今後の通貨形態を予測しつつ、 誰にとって有利な社会構造へと変容しているかを知るという内容であった。(本ブログをご覧の皆様は、当然の教養として株式投資や仮想通貨について詳しくご存じだろう。しかし、これらの話題は学校で詳細に扱うことはほとんどなく、同テーマの課外活動やイベント等に積極的に参加するか、自由に使える資金が限られる中、独学で身につけようとしない限りこの分野の教養はなかなか身につかないものである。)普段講師・原田武夫のレクチャーを受けている優秀な学生を相手に約90分間の講義を担うのは重責であったが、昨今のニュースを取り上げつつ、入社してから間もなく弊研究所代表・原田武夫から筆者に課された“金融課題*”に触れるなどし、ひとまず役を終えることができた。(*金融課題:自ら選んだ企業の株価を約3か月間毎日観測し、特定の株価と日経平均株価・その他指標がどのような関係性にあるかを予測しながら追っていくというもの。)
さて、おさらいということにはなるが、弊研究所が考える“情報リテラシー”を端的に示すと、「過去に対する偏りのない正しい認識とそこから導き出される歴史法則をベースにしながら、未来志向のロードマップを創り上げる能力」である。弊研究所のヴィジョン“Pax Japonica(パックス・ジャポニカ)”実現のために行う社会貢献事業の中核を担うのは、明日の人財を育てる「教育」であると考えている。弊研究所は、国内外の学生に対して、講義・読書会・インターンシップという形で“情報リテラシー”の内容を含むアントレプレナーシップ教育を積極的に推進してきたが、これは「アントレプレナー」、つまり「0→1」ができる人財を育てることが、結果的に我が国に「明日のビジネスを作り出す人財」を生み出すことに繋がり、我が国に「ポジティヴな循環」を齎すことを指すからである。
弊研究所会員制サーヴィス「原田武夫ゲマインシャフト」会員の皆様の中にはご存じの方がいらっしゃるかもしれないが、弊研究所では、上記のような学生対象の教育活動のみならず、会員様=成人に対する教育活動も行ってきた過去がある。2023年には、弊研究所が姉妹団体である一般社団法人日本グローバル化研究機構(RIJAG)と共催の下、「社会的包摂のための“慈愛”プロジェクト(Compassion for Social Inclusion)」と題して、無料の連続講演会を開催した。現在においては幅広く知れ渡っている“No One Left Behind(誰一人取り残さない)” 、「社会的包摂 (Social Inclusion)」が、特に我が国国内において問題解決が滞っているとの指摘が強く成されていることに弊研究所は課題を感じていた。そうした中で、我が国はいよいよ資産バブルの時代を迎え、怒涛の如く押し寄せるグローバル・マネーを前に社会的包摂の対象とされる方々に対し、我が国社会が大きく変わろうとしている現代だからこそ、そもそもこうした社会的包摂を必要とされる方々がどういった実態を孕むものであるのかと同時に、いかなる形で新しくグルーバル社会に包摂されていくべきなのかを議論する場を設けたのがこのプロジェクトであった(詳細はこちら:社会的包摂のための“慈愛”プロジェクト(Compassion for Social Inclusion))教育は何も子どもたちのみが対象というわけではないのである。
上記のように、教育活動に精力を注ぎこれまで様々な社会貢献事業を展開してきた弊研究所が、2025年度も引き続き変わらぬ熱い想いで教育活動に従事していくことを前提としつつ、最後に我が国の教育に対する卑見を述べたいと思う。
我が国の教育と言えば、常に「大人から子ども」への一方的な教育体系を思い浮かべる。これに疑問を持ちオルタナティブ教育に興味を持った筆者だが、そこからの気付きと言えば、一つには家庭教育の大切さである。幼児期から青年期に至るまでの教育は、年齢と共にその質や中身が変わる。しかしそのどの段階でも普遍的かつ重要なのが、家庭での子どもへの接し方であり、教育である。しかし、家庭教育は親、保護者の義務であり役割でもあるがゆえに第3者からの口出しは容易にできないという難しさがある。大学生ともなれば、次第にアルバイト代という“自由に使えるお金”を持つ学生も少なくない。経済的余裕によって個々人が移動できる範囲が一気に拡大するため、それに伴い関わる大人の数が増え、自分の世界がどれほど小さかったかを目の当たりにすることになる。一度広い世界を知ったならば、そこから先は自分次第でいくらでも知の探索は可能だ。弊研究所としてはこの段階以降の学生らに対して“情報リテラシー”教育、アントレプレナーシップ教育を実施していることになる。しかし、それ以前の家庭教育のウェイトが計り知れないこともまた事実であるのだ。親、保護者と、保育施設、学校、塾の先生がよく知る大人全てであった頃の、大人から子どもに対する関わり方の影響力は良くも悪くも絶大である。特に、生活時間の大半を過ごす家庭での“学び”の割合は大きいのだ。子どもが自らの力で“立つ”前に、彼らが生きる環境に存在する大人は、その役割を今一度考えるべきであると考えるが、いかがだろうか。
※当ブログの記述内容は弊研究所の公式見解ではなく、執筆者の個人的見解です。
事業執行ユニット 社会貢献事業部 田中マリア 拝
ご覧いただき、ありがとうございます。本ブログに対するご感想などは、ぜひこちら(https://form.run/@bdg-gGcHeNdjRAhgMh17v3uQ)までお寄せください。
【筆者プロフィール】
田中マリア:高校2年次と大学4年次にそれぞれ約1年のオランダ留学を経験。大学では、オランダ学と社会教育学を専攻し、卒業論文は「日本の初等教育の改善-モンテッソーリ教育からの示唆-」というテーマで執筆した。大学卒業後は、一般保育園にてフリー保育士としてパート勤務をしながら、国際モンテッソーリ教師資格(3-6歳)を取得。2024年4月より株式会社原田武夫国際戦略情報研究所ヘ入所。現在、社会貢献事業を担当する。
★詳しい自己紹介はこちら→コーポレート・プランニング・グループの”自己紹介” ブログ(Vol. 4)
[関連記事](タイトルをクリックすると記事へ飛びます。)
・平田篤胤はなぜ日本語研究に勤しんだのか (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.24))
・巳年と蛇と柳田國男 (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.23))
・「想いの伝承」を可能にするその方法とは何か。 (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.22))