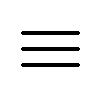巳年と蛇と柳田國男 (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.23))

早いことに2025年も1か月が過ぎたが、今年は巳年である。
脱皮を繰り返して成長する「蛇」は再生の象徴ともいわれる。古い固定観念を脱ぎ捨て、新たな視点で世界、我が国、そして自らの人生に向き合う良い機会であるのではないだろうか。
さて、弊研究所に所蔵されている書籍を漁っていたところ「完本 天の蛇―ニコライ・ネフスキーの生涯」というタイトルが目に入った。「巳年のブログにぴったり!」と本を手に取り、目次を眺めると、馴染みのある名前書かれていた。「柳田國男」。確か地元に記念館があった。小学校の近くに佇む柳田國男館。町の中心から少し外れたところにある。小学生のころからその名前は知っていたものの子どもの筆者にとっては何も魅力を感じなかった。そんな“有名人”に今日、本棚で再会したのだ。きっとこれも何か意味のあるタイミングなのだろう。この機会に彼について少し掘り下げてみようと思う。
柳田國男は、1875年7月31日現在の兵庫県神崎郡福崎町に生まれ、1962年8月8日に亡くなるまで多くの功績を残した多彩な人物である。幼少期に体験した飢饉、故郷を離れて見聞きした庶民の暮らしや間引き慣習の悲惨さを思い、「経世済民の学」を志向し、東京帝国大学法科大学(現東京大学)で農政学を学んだ。大学卒業後には農政官僚となり、明治34年に信州飯田藩出身の柳田家の養嗣子となる。視察や講演旅行で日本各地の実情に触れ人々への関心を深め、文書に書かれた政治や事件が中心の従来の歴史学を批判。名もなき庶民の歴史や文化を明らかにしたいと考え、「常民文化の探求」と「郷土研究」 の必要性を説いた。
「日本民俗学の父」とも呼ばれる柳田國男は、古くから伝えられてきた話や土地に伝わる話を調べ、上記のように「私たちの過去を知る」ことに力を入れて取り組んだ。岩手県遠野市に伝わる逸話、伝承などを記した説話集「遠野物語」や、言語学においても日本語の成り立ちや方言に関する深い洞察を提供してきた「蝸牛考」などの著作をご存じの方も多いだろう。
(『遠野物語』:民話研究家である佐々木喜善から伝え聞いた民話に、現地での見聞・調査による補完を加えたもの。村内の池沼や里山、獣など自然にまつわる由来や伝承だけでなく、河童の存在といったあやかしの類にも触れている。臨死体験をした男の話、幽霊、魂の供養、豊穣祭、山姥など実に多種多様な風習・信仰・民話が語られていく。『蝸牛考』:カタツムリ(蝸牛)の語形分布を例に、文化的中心地から地方に言葉が伝播し、中心から遠い地方に古い語形が残るとする考え方とされる“方言周圏論”に基づく学説。方言周圏論は、方言の分布を解釈する基本的な考え方として現在でも有力な見解の一つである。)
戦中、戦後においても民俗学の研究を続け、百冊を超える主著を含め、その膨大な業績は「定本柳田國男集」に収載されている。1951年には文化勲章も受章するなど、彼の収めた功績は大きい。
(写真:柳田國男)

(参照:国会図書館)
さらに柳田國男について調べていると「エスペラント」という文字が目に留まった。エスペラント語とは、簡潔には世界中にある7000以上の言語の壁を越えるための新言語であり、ユダヤ系ポーランド人のルドヴィコ・ザメンホフ(1859-1917)とその協力者たちが考案・整備した人工言語である。弊研究所所員によると、このエスペラント語は言語学オリンピックの問題にも出題される言語だそうで、マニアックな言語であることは間違いないだろう。(弊研究所には物知りな所員がいるのです笑)
柳田國男は1922年(大正11年)、新渡戸稲造と共にエスペラントを世界の公立学校で教育するよう決議を求めていた。エスペランティストのエドモン・プリヴァ(Edmond Privat)と交流し、自身もエスペラントを学習し、1926年7月には財団法人日本エスペラント学会設立時の理事に就任している。(筆者が学生時代、ディベートの講義で割り当てられた発表テーマがエスペラント語だったのを思い出しました。)
少し前にこの社会貢献事業ブログでも言語、特に日本語のハイコンテクストについて取り上げたが(ハイコンテクストな日本語は得か? -“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.19)-)、言語を一つのきっかけに文化に強い関心を覚え、これを追求することは、その環境で生きる自らを知るプロセスともいえるだろう。柳田國男も、「日本語」を日本という空間に密着した「統一体」として存在していると認識していたという。彼は、その日本語を読み解くことで自らのルーツや存在意義を明らかにしようとしたのかもしれない。
また同時に他言語を学ぶことは自分の視野や価値観を広げることに直結する。弊研究所代表・原田武夫も「日本語、英語、そして最低もう一か国語習得することが望ましい」と話していた。多言語の習得は同時に相手を慮るということでもある。観光客の方が日本語で「ありがとう」と声を掛けてくれたのならば、“Thank you.”と言われるよりも嬉しいものである。エスペラント語は特定の民族や国、地域と対応していないため、自らの母語を他者に押し付けることなく他者と歩み寄る姿勢を持つことができる。したがって異なる民族に属する人々の間の相互理解を目的としたエスペラント語の習得を図った柳田國男は、ある意味で究極の平和主義者と言えるかもしれない。
ここまで書籍「完本 天の蛇―ニコライ・ネフスキーの生涯」から派生し、柳田國男について書いてきたが、最後にニコライ・ネフスキーについても少し触れよう。
ロシア人ニコライ・ネフスキーは、1909年サンクトペテルブルグ大学東洋語学部へ入学後、日本学者・西夏学者となった。その後23歳の頃から14年間に渡り日本に滞在し、深く日本語と日本文化を研究した。
(写真:柳田國男の第1回渡欧を記念するために折口信夫宅の庭前で撮影。
前列向かって右から柳田國男、ネフスキー、金田一京助。後列左端が折口信夫。)

(参照:はてなブログ-Le ciel bleu sur Europe ヨーロッパに広がる青い空-)
コンラドは当時東京大学に通っていたが、ネフスキーは独学で日本の古代文化の研究を始めた。彼はまず祝詞の研究に関心を寄せた。また神道が日本人の生活の中でどの様な形で生きているか調査しようと考え、この分野における日本人研究者と知り合いたいと思っていた。そしてその希望を、よく出入りする古書店の主人にも伝えた。古書店と研究者たちとの人間的な交わりは、今でもわずかながらよき伝統として残っている。その当時は、両者の関係はもっと密接だったに違いない。コンラドとネフスキーとは、店主を通じてその目的のために絶好の日本人、中山太郎を紹介されたのである。[加藤11, pp.70-71]
上述のニコライ・コンラドは「ソ連における日本学の父」といわれ、日本文学、日本史、日本語について多くの著作を残し、また優れた学者・翻訳者を多数養成した大学者である。ソ連では、彼のことを知らない日本学者は一人もいないと言われていたという。ネフスキーとコンラドは、ロシア革命前後の怒涛のような時代における若き日本学徒として、生涯の盟友になったのである。そして上記のような経緯から、民衆史の立場から歴史的な文献を多く用いて多方面の民族史を書いた人物である中山太郎と出会い、また彼を通じて柳田國男、折口信夫、金田一京助、山中共古、佐々木喜善らに紹介されたのである。書籍には以下のように書かれており、柳田國男とネフスキーの良好な関係性が伺える。
「柳田国男とネフスキーとの間はその後急速に親しくなり、一九一六年(大正五)ニ月、ネフスキーのニ五歳の誕生日には、柳田の方から駒込林町の彼の自宅を訪れている。[加藤11, p.72]」
さて、今回は我が国の民俗史を深く愛した柳田國男について取り上げ、海の向こうからやってきた日本学者、ニコライ・ネフスキーについて簡単に紹介した。内側から見る日本と外から見る日本はどのように違って見えるのだろうか。引き続き、関連書籍を読み進めたいと思う。
【参考文献】
・[加藤11] 加藤九祚, 「完本 天の蛇―ニコライ・ネフスキーの生涯」, 河出書房新書, (2011).
※当ブログの記述内容は弊研究所の公式見解ではなく、執筆者の個人的見解です。
事業執行ユニット 社会貢献事業部 田中マリア 拝
ご覧いただき、ありがとうございます。本ブログに対するご感想などは、ぜひこちら(https://form.run/@bdg-MFKGbergsFLJHirabRHz)までお寄せください。
・
【筆者プロフィール】
田中マリア:高校2年次と大学4年次にそれぞれ約1年のオランダ留学を経験。大学では、オランダ学と社会教育学を専攻し、卒業論文は「日本の初等教育の改善-モンテッソーリ教育からの示唆-」というテーマで執筆した。大学卒業後は、一般保育園にてフリー保育士としてパート勤務をしながら、国際モンテッソーリ教師資格(3-6歳)を取得。2024年4月より株式会社原田武夫国際戦略情報研究所ヘ入所。現在、社会貢献事業を担当する。
・
[関連記事](タイトルをクリックすると記事へ飛びます。)
・「想いの伝承」を可能にするその方法とは何か。 (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.22))
・人工知能(AI)、巳年天井なるか。(“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.21))
・平和の女神“Pax”が語る世界イメージとは何か?(“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.20))