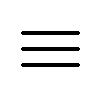「想いの伝承」を可能にするその方法とは何か。(“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.22))

「そういうことだったのか。」
東野圭吾作「クスノキの番人(2020)」を読み終えたときの率直な感想だった。ここからはネタバレを含むため、同書を読まれるご予定の方は、読了された後本ブログヘ戻ってきていただきたい。
●クスノキの番人あらすじ
その木に祈れば、願いが叶うと言われているクスノキ。その番人を任された青年と、クスノキのもとへ祈念に訪れる人々の織りなす物語。
不当な理由で職場を解雇され、その腹いせに罪を犯し逮捕されてしまった玲斗。同情を買おうと取調官に訴えるが、その甲斐もなく送検、起訴を待つ身となってしまった。そこへ突然弁護士が現れる。依頼人の命令を聞くなら釈放してくれるというのだ。依頼人に心当たりはないが、このままでは間違いなく刑務所だ。そこで賭けに出た玲斗は従うことに。依頼人の待つ場所へ向かうと、年配の女性が待っていた。千舟と名乗るその女性は驚くことに伯母でもあるというのだ。あまり褒められた生き方をせず、将来の展望もないと言う玲斗に彼女が命令をする。「あなたにしてもらいたいことーーーそれはクスノキの番人です」と。
(Amazonより抜粋)
クスノキが立つのは月郷神社である。新月の日にクスノキを訪れ、この世に残したい「想い」をクスノキに向かって念じる。これが“預念”である。これに対し、クスノキのパワーが最も大きくなる新月の夜にその「想い」を受け取ることが許されるのは、血縁関係のある家族のみである。これが“受念”である。受念で受け取ることができるのは、預念者が特に伝えたいと念じたイメージや音はもちろんだが、少なからずそれに交じって伝わってくるのが、それまでの人生で感じた複雑な預念者の感情全てである。
複雑な感情とは何か。筆者が「血縁関係のある家族」とわざわざ枕詞を加えた理由を推測してほしい。それがカギとなるということはつまり、世の中に巨万といる血縁関係のない家族の事業継承が同書のトピックの一つであるということである。
クスノキは、何層にも重なり複雑に絡み合った人間関係の模様や自らの過去の過ち、進行を止めることのできない病に対する気持ちなど、預念者の深層心理の想いを意図せず家族へ伝えてしまうこともある。そのため自らの死を悟り、自らの全てをさらけ出す覚悟ができたとき、この不思議なクスノキを遺言書として使う人が多いという。預念者はもちろん、受念する方もこれまで知らなかった事実を突きつけられることになる可能性があり覚悟が必要なのである。
(写真:大山祇神社の楠(愛媛県今治市))

(参照:ひろしま公式観光サイト)
さて、これが弊研究所の社会貢献事業とどのように関係するのかと疑問に思われているかもしれない。
上述のようなクスノキが現実に存在するのなら訪れてみたいが、残念ながらそれはファンタジーの世界のようだ。しかし現実世界で同様の「想いの伝承」ができるとすれば、興味が湧いてはこないだろうか。ここで人工知能(AI)の出番である。
近年、人工知能(AI)の技術を用いた企業のマニュアル化や、膨大なデータを一つのデータベースにし、それを使用したChatbotの作成などが進んでいる。つまり、特定のコミュニティに対して残したい「想い」を保存することが可能なのである。この場合、クスノキとは異なり深層心理が意図せず受け取り手に伝わってしまう心配はない。後世に残したい“情報”のみを取り出して届けることができるのだ。「想い」を誰の目から見ても明らかな状態、つまり文字データとして保存するため、受け取り手にとってわかりやすく優しいという点もメリットだろう。
同書を読み終えたとき、「自分の親が預念するならば、何を想うだろう」と考えた。筆者に子どもがいれば、何を遺したいか真剣に考えるだろう。今このブログを読んでいる一人ひとりが“預念者”であり“受念者”でもある。物語の中では、不思議な力を持ったクスノキは月郷神社にしか存在しないわけであるが、人工知能(AI)の技術は誰もが学び習得することができる。そして弊研究所は、その知識・技術を持っているのである。
2025年、我が国の「団塊の世代」全員が後期高齢者となる。これに伴い、彼らが持つ“知恵”や“匠の技”が失われずに後世へと引き継がれることの重要度が高まっていると感じる。すなわち、国民の5人に1人が75歳である超高齢社会を迎える我が国は「想いの伝承」という大きな社会課題に直面しているのだ。それらの想いが後世に引き継がれることは、我が国の知恵伝播・技術伝承そのものであり、これが弊研究所のヴィジョン“Pax Japonica”の実現を促進すると考えている。これを2025年度の社会貢献事業の中核に据え、東野圭吾作「クスノキの番人(2020)」よりインスピレーションを受け、「クスノキ・プロジェクト」を立ち上げることとした。
近年の自然言語処理(Natural Language Processing、NLP)及び大規模言語モデル(Large Language Models、LLM)に関する研究成果をベースに日本全国を行脚しながら、弊研究所会員制サーヴィス「原田武夫ゲマインシャフト」の会員様をはじめ、広く一般の皆様に対しても、無償のプログラミング講座「クスノキ・AI講座」を実施したいと構想を練っている。主役はあくまでも参加される方々であり、それぞれが抱えられている「事業継承」のお悩みを解決するため、弊研究所設立から17年間に及ぶ知恵をフル活用する所存である。今後は、読者の皆様よりご意見を賜りながら、プロジェクトをさらに形作っていきたい。
※当ブログの記述内容は弊研究所の公式見解ではなく、執筆者の個人的見解です。
事業執行ユニット社会貢献事業部 田中マリア 拝
ご覧いただき、ありがとうございます。本ブログに対するご意見やご感想は、ぜひこちら(https://form.run/@bdg-7NBunXlkygt5DGDQFmcd)までお寄せください。
・
【筆者プロフィール】
田中マリア:高校2年次と大学4年次にそれぞれ約1年のオランダ留学を経験。大学では、オランダ学と社会教育学を専攻し、卒業論文は「日本の初等教育の改善-モンテッソーリ教育からの示唆-」というテーマで執筆した。大学卒業後は、一般保育園にてフリー保育士としてパート勤務をしながら、国際モンテッソーリ教師資格(3-6歳)を取得。2024年4月より株式会社原田武夫国際戦略情報研究所ヘ入所。現在、社会貢献事業を担当する。
・
[関連記事](タイトルをクリックすると記事へ飛びます。)
・人工知能(AI)、巳年天井なるか。(“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.21))
・平和の女神“Pax”が語る世界イメージとは何か?(“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.20))
・ハイコンテクストな日本語は得か? (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.19))